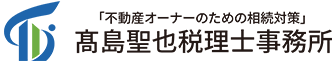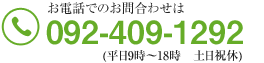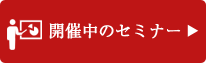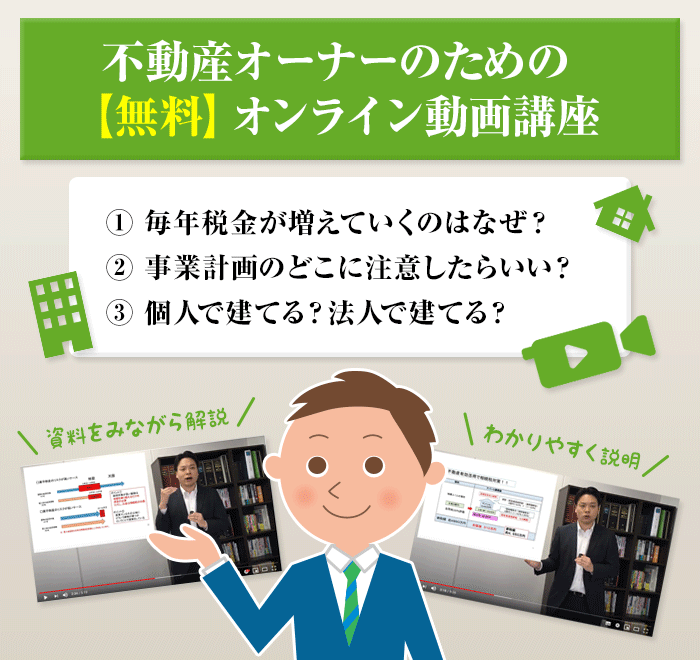近年、建築費の高騰が続いています。
一方で家賃は上昇傾向にあるものの、その上昇幅は建築費に追いついておらず、
2〜3年前と比べても建築を取り巻く状況は非常に厳しくなっています。
こうした厳しい環境下でも、土地の有効活用や相続対策の一環として、
建築を行わなければならない場面があります。
そのようなときに、以前にも増して「失敗が許されない」ということを
強く感じるようになりました。
ここで言う「失敗しない」とは、市場のニーズにしっかりと合致し、
かつ収支のバランスが取れた建築を行うということです。
さらにケースによっては、相続対策としての効果を発揮できるものである必要もあります。
市場のニーズを把握するには、建設会社やその設計士の協力が不可欠です。
私自身、建設会社の設計士や営業担当と打ち合わせをする中で、
「なぜこの点に気づかないのだろう」と疑問を抱くことがありました。
たとえば、入居者がスムーズに建物に入れるような動線設計ができているのか、
実際に生活する際に必要となる家具のサイズや配置が考慮されているのか、
といった基本的な視点が抜けていることがあります。
近年では、ライフスタイルの多様化により家具のサイズやデザイン、
必要とされる機能も変化しています。
ダイニングテーブル一つとっても大きさは家庭によって異なり、
生活スタイルによってリビングの使い方も様々です。
そのため、設計段階であらかじめ最新の家具の大きさに合わせた間取りや、
入口・通路の幅を考慮しておくことが必要です。
むしろ、家具から暮らし方を逆算し、暮らしのコンセプトを明確にしたうえで、
それに即した間取りを考えるといった設計のアプローチが求められていると感じます。
こうした多様化したニーズや暮らしの在り方を掘り下げ、しっかりと提案できなければ、
入居者に高い家賃を納得して支払ってもらうことは難しい時代です。
暮らしに対して価値を感じてもらえる空間でなければ、選ばれる物件にはなりません。
また、もう一つ大事な点は「無駄をなくすこと」です。
建設の現場では、わずかな設計のズレや認識の違いが、
最終的に無駄な建築費を生む原因となります。
建設費が高騰している今だからこそ、余計な要素を省き、
シンプルかつ機能的な設計を徹底することが、結果としてオーナーの
収支を安定させるカギになります。
つまり、少しのズレが「ただ建築費が高くなるだけ」の状況を招くということです。
これからの提案においては、営業担当者や設計士もこうした市場調査やニーズ分析、
そして実際の暮らしを起点とした設計に積極的に取り組むことが、
「失敗しない不動産建築」への第一歩だと確信しています。
なお、あるハウスメーカーでは、設計士が「相続税対策を前面に出す」ことを
当然のように語っていたことがありました。
これは本末転倒ではないかと感じました。設計士は本来、
良い建物をどう作るかを真剣に考えるべきであり、会社としてもその方向に
集中できるよう教育すべきです。
お客様のニーズ、そして自社が提供すべき価値をしっかり理解したうえで、
建築の提案を行うことが極めて重要だと考えます。
私自身も、家電量販店などに足を運び、最新の情報を取り入れていきたいと思っております。
もし皆さまから「今の市場はこうなっている」といった情報があれば、
ぜひ共有していただけると幸いです。
令和7年5月9日 税理士 髙島聖也