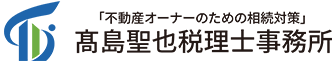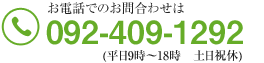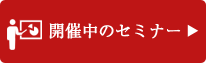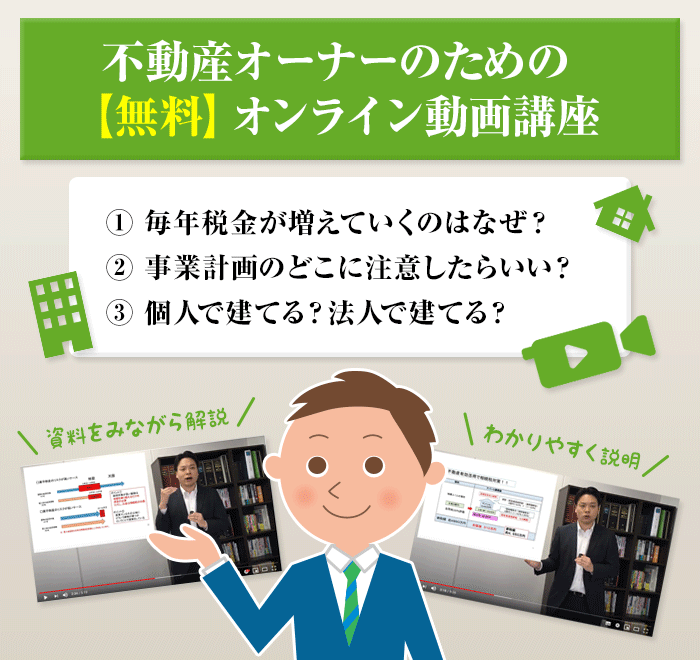不動産経営における戦略自由度
不動産を活用した相続対策を考えるうえで、私が非常に大切だと思うのは、
「その対策によって家族が本当に幸せになれるのか」という視点です。
相続対策を実行した結果、「あのとき対策を立てておいて本当によかった。
おかげで家族が幸せになれた」と思えるのであれば、
その対策はとても意義があると思います。
しかし一方で、「親があんな対策を立てたせいで、私たちは大変な思いをした」という声も
少なくありません。
実際には、そのようなケースに陥っている方が多いのではないでしょうか。
「このままでは財産がなくなってしまいますよ」という一言をきっかけに、
アパートやマンションの建築を進め、所有している土地すべてに建物を
建ててしまう方もいらっしゃいます。
では、そのようにして本当に資産を守ることができたのでしょうか。
土地の上に建物は残っても、相続税をなんとか支払った結果、
今度は所得税の負担や新たな借入が難しくなるなど、経営的に行き詰まってしまうケースも少なくありません。
私は、相続対策を「将棋」に例えることがあります。
つまり、「その一手を打つことによって、
次の一手、その次の一手まで考えているのか」ということです。
一つの手を打った結果、その先の選択肢がなくなってしまうようでは本末転倒です。
そうならないためには、場面の展開を常に想定し、
「この一手を打ったらもう引き返せないのではないか」という視点を持って
判断していただきたいと思います。
たとえば、相続税対策としてアパートを建築したとします。
その物件が相続税対策としては有効でも、収支としてあまり魅力的でない場合には、
他の物件でカバーできるかどうかを検討する必要があります。
もし他でカバーできないようであれば、その一手を打つことで経営が行き詰まり、
結果的に「賃貸経営として負けてしまう」ことになるかもしれません。
そうした場合には、「別の一手」を考えてみることが大切です。
たとえば、売却という選択肢もありますし、別の物件を購入するという方法もあります。
あるいは、思い切って「相続税を払う」という選択肢もあっていいのではないでしょうか。
このように、複数の選択肢、つまり「次の一手」を考えておくことが重要です。
また、ご自身にとって身軽なポジションを取ることで、より安心した経営ができると思います。
この「次の一手を考える力」こそ、後継者の方々にぜひ身につけていただきたい力です。
残念ながら、このような発想を持つ不動産営業担当者少ないのが実情です。
なぜなら、建築を勧めることや物件を販売することが目的化してしまい、
「手段が目的」になってしまうからです。
だからこそ、「次の一手を生み出す力」、つまり戦略自由度を高めていただきたいと思います。
なぜこのようなことを申し上げるのかというと、
良い経営をされている方ほど、この戦略自由度が高いからです。
「これがダメなら次を考える」「次がダメなら別の策を打つ」「その次がダメでも別の道がある」。
このような柔軟な姿勢こそが、資産を守り抜く力になります。
つまり、資産を守るためには、戦略自由度を高めるためのポジショニングを、
無意識のうちに取っておくことが大切なのです。
令和7年10月7日 税理士 高島聖也